SFプロトタイピング小説 公開!『海が囁くとき』前編
この度、京セラでは、SF作家の先生とコラボレーションし、エネルギー分野の未来を考えるSFプロトタイピング・ワークショップを開催。ワークショップでのインスピレーションをご活用いただきつつ、林譲治先生にSFプロトタイピング小説『海が囁くとき』をご執筆いただきました。
全3回(前編・中編・後編)に分け、SFプロトタイピング小説『海が囁くとき』を公開いたします。
今回は前編をお届けします。どうぞお楽しみください。
海が囁くとき<前編> 林譲治
「浮上時間三〇秒前、データ受信準備! 」
潮マヤの視界の仮想空間の中で、船の調査デッキの光景が浮かぶ。マヤはすぐに自分がいるラボデッキに視界を戻す。
正面の情報共有モニターには中心に海洋調査船バラクーダが置かれ、緑色で四〇基あまりの海中探査ドローンの推定位置が表示される。
それらのドローンは三〇秒後に浮上し、衛星通信経由で、担当エリアの海洋の状況をバラクーダに報告する。データ分析だけなら地上でも可能だ。ただ、何か異変があった時に、精密な調査を行うには、移動研究所でもあるバラクーダの機動力が物をいうのだ。
「ボスは週末はどうするんですか?」
隣席でモニターを見ているサブボスのキア・キアがマヤに尋ねる。残り三〇秒のこのタイミングで、なぜそんなことを尋ねる、と思いつつも、マヤは答えた。
「
「いえ、週末どう過ごそうかなぁ、と思って参考に。みんな外に行くのかぁ」
「ずっと船で生活してるんだから、休暇くらい人工島じゃなくて、普通に陸地に行きたいじゃない」
「そうですね、海嘯35にしても、まぁ、船ですよね、あれも」
会話は浮上したドローンからのデータ受信の開始とともに終わる。空気が読めないようで、キア・キアもそこはプロだ。
「えぇっ! 」
キア・キアが奇声を上げたが、驚いた点ではマヤも同じだ。ドローンの浮上位置が、どれも数メートルほどだがどれもずれている。しかし、そんなことは海流の関係で起こりがちだ。問題は、四〇基あまりのドローンからのデータすべてが、異常を示す赤の点滅で表示されていることだ。
「ボス、赤の点滅って、装置の故障ですよね」
そうマニュアルには記載されていたが、マヤは赤い点滅の背景を分析していた。
「ドローンすべてが同時に故障することは確率的に考えられない。分析AIが装置の故障を報告するのは、ドローン本体のAIが異常を報告したときと、ドローンからのデータが明らかに矛盾している場合」
「ドローンの調査エリアに何か、AIがありえないと判断するような異変が起きているということですか? 」
キアはすぐに問題の本質を理解してくれた。だから彼女は帰属は違えどマヤのサブなのだ。
「まず、データ分析。AIが何を考えて、こんな注意喚起を行ったのか? 」
「すべてのデータ受信の終了後に会議開催」
「ドローンは浮上したままセルフチェックさせます? 」
キアの指摘は的確だった。
「セルフチェックしましょ。それと一番近いドローンはバラクーダで回収。そちらは人間様がチェックする」
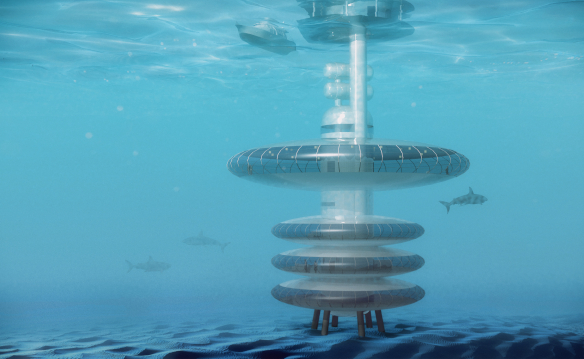
海洋調査船バラクーダは太平洋をフィリピン方面に向かって航行していた。積載量八〇〇〇トンという数値は、全長五〇〇メートルの大型船も珍しくない二〇五〇年の基準では小型船に思えたが、八〇人の乗員にとっては十分大きな船であった。多様な調査活動に対応するため空間に余裕があるため、作業内容によってはバディ以外に他人の姿を見ないことさえあった。
八〇人の乗員のうち、バラクーダの航行に必要な人間は一〇人ほど。船医や料理人などの支援要員一〇名をのぞく六〇名は、各種の調査活動に従事する専門家だった。
小さな調査船では、加工済みの食料品を当番で配膳するのだが、バラクーダのような船舶では専属の料理人が乗っている。娯楽の少ない船舶では食事が重要なイベントであるからだ。料理の質が高いと士気も上がって作業効率もあがるのだ。
バラクーダは船の保有者、運用チーム、調査チーム、支援チーム、それぞれが別々の企業や組織に属している。たとえば調査船そのものは日本の海上自衛隊の保有であるが、自衛隊員は経理部長と部下一人だけで船長以下の運行要員は複数の企業体に属していた。調査チームのリーダーである潮マヤも同様で、いわゆる同僚もここには二人しかいない。
これは今日ではさほど珍しいことではない。通信コストの劇的な低下と輸送技術の進歩、さらにはAI自動翻訳機能による言葉の壁が無視できるようになり、ほとんどの国で、国民は国境を超えた人間関係や組織に属していた。個人が自分の会社を持ち、それらがAIによるマッチングにより、時にはチームを組んで一つのプロジェクトを完遂することもありふれた光景となっていた。

このため国家という枠組みこそ存在していたが、国民の多くにとってナショナリズムは意味を失いつつあった。抽象的なナショナリズムよりも個人にとって、自身が帰属意識を持つ集団は幾つも存在したからだ。
潮マヤの調査部門のリーダーという職務も調査チーム間の調整や調査計画の立案などが主なものだった。むろん命令権限はあるが、それはリーダーとしての職務に付随するもので、命令を出せるのは就業時間だけである。複数団体に帰属するメンバーのチームであるから、職務上の上下関係はプライベートにまでは持ち込まれることはない。それが今日の国境を超えて働く人間の常識であり、共通文化でもあった。
「バラクーダのAIが異常と判断した理由ですが、ここ数日の天候から予想される海水温とドローンが計測した海水温の間に数値のズレが予測される誤差以上に大きかったためです。特に海面表層の温度差で顕著で、深層の海水温は予測値とほぼ変わらない」
バラクーダのAI担当部門の代表が、分析結果をモニターのなかで報告する。調査チームは船内で分散して作業にあたっている。会議のために一つに集まるのも非効率だ。それにチームごとに分散していることで、海難事故などで指揮系統が全滅するリスクも回避できる。
海洋調査船という性格から、海底火山の噴火のような危険な調査も行われるし、数は減っても未だ海賊もいれば、国境紛争海域もある。万が一に備えることは不可欠だ。
魚のバラクーダは海のギャングとも呼ばれるが、本船には放水銃以外に武装はない。ただプロジェクトによっては、武装した危機管理チームのメンバーが乗船したり、護衛艦艇が就くこともあった。昨今はそうしたセキュリティ関連サービスも当たり前にビジネス化されている。その分、警察や軍隊の存在感は低下していた。
「つまり海面表層の温度がシミュレーションの予測値より有意に高い。しかし、それ以外はシミュレーションと合致している。細かいモデルの修正で、シミュレーションの再現性はいままでの経験から立証されている。それでも表層温度だけがシミュレーションと異なるのは、モデルの問題と言うより、海洋の表層で、何か見落としがあるということね」
「でも、このシミュレーションも実績を積んできたものです。いまここで見落としが見つかるというのも納得できませんね、正直」
マヤにはキアの言い分もわかる。気象や海象を予測するシミュレーションモデルの歴史には、数十年の積み重ねがある。それがいまここで見落とされていたものが見つかるというのは、やはり考えにくい。
「大型船舶が通過して、冷却水を放出したんだろうか? 」
それは会議に参加している機関長の発言だった。調査チームのメンバーではないが、調査計画を立て直す可能性もあり、そうなれば乗員の協力は不可欠なので、マヤは彼らにも参加を呼びかけたのだ。
「ドローンの探査範囲と大型船の航路が偶然重なれば、あり得なくはないですね」
マヤがそう言っている間に、キアは周辺の船舶の航行状況を調べていた。ただマヤは機関長の説も可能性は低いと思っていた。調査海域は主要航路から外れているのと、海水温度をこれだけの領域で上げられるとなれば、沸騰した海水をかなり大量に流さねばエネルギーの帳尻が合わない。
「残念ながら、この数日の間に調査海域に入った大型船はありません」
「よし、それならドローンチームは、無人機による航空偵察を行って。海水温が具体的にどれだけの範囲でシミュレーションとずれているかを調べましょう。それで未知の熱源が見つかるかも」
すぐにバラクーダからは、二機の固定翼型ドローンが時間差をおいて発射された。それで同じコースを進ませ、温度変化の動きを見るためだ。結果は数時間後に出た。
「まず表層の海水密度が低いために、木星の大赤斑のように動かない領域が予想以上に広範囲に存在しています。問題となる表層海水温度の上昇域は、この孤立領域の内部に存在しています。低密度領域との関係もいまのところ不明です」
マヤの話に調査チームの全員が困惑していた。
「ここで外部からエネルギーの供給があると仮定した場合、シミュレーションの結果は観測された事実と合致します。つまり我々の見逃しているエネルギー流入がこの海面温度の上昇領域にある」
その言葉にミーティング空間にざわめきが起こる。それが収まるのを待って、マヤはもう一つの観測結果を示した。
「因果関係は不明ですが、本件と高い相関関係がある事実が見つかっています。この高温域には大量のイワシの群れが見つかっています。沿岸部で生育するイワシは、通常はこんな海域では認められないのに」

(続く)
著者:林 譲治(はやし じょうじ)
1962年2月 北海道生まれ。SF作家。日本SF作家クラブ会員(第19代会長)。
臨床検査技師を経て、1995年『大日本帝国欧州電撃作戦』(共著)で作家デビュー。
『ウロボロスの波動』『ストリンガーの沈黙』『ファントマは哭く』と続く《AADD》シリーズをはじめ、『小惑星2162DSの謎』(岩崎書店)『記憶汚染』『進化の設計者』(以上、早川書房刊)など、科学的アイデアと社会学的文明シミュレーションが融合した作品を次々に発表している。
《星系出雲の兵站》シリーズ(早川書房)にて第41回 日本SF大賞受賞。
最新刊は『大日本帝国の銀河」シリーズ』(早川書房)。
家族は妻および猫(ラグドール)のコタロウ。



